HIROSEのミュージックバーへようこそ。こちらのブログでは、音楽を中心としたさまざまな情報を気まぐれに発信しています。
今回は、タイトルにもある通りですが…
日本における”夏”を考察します。
我が国特有の夏に対する概念的な意識を、できる限り言語化してみようという試みです。
この、言語化でき得ない概念に対する研究は、私が人生を通して解明していきたいテーマでもあるのです。
とはいえ、全てが難しい話というわけではありません。緊張感のある導入になりましたが、簡単に「夏休み」や「海水浴」、「祭り」のような楽しい側面が夏の主なイメージでしょう。
長々と失礼しました。それではどうぞ(^^)
【① “SUMMER”の夏】
まずは、SUMMERの夏とかいうクソ語彙で失礼なのですが、いわゆる一般的なイメージの夏です。前述した、「夏休み」や「海水浴」、「祭り」などのポップなイメージは、どれも夏と聞いて想起するものばかりだと思います。
難しいことを考えずに、感覚的に夏を思い出すと、少年時代のセミ捕りや川遊びなどの思い出が蘇りますよね。
音楽的には、ORANGE RANGEや湘南乃風、TUBEなどがこれらに該当すると思います。夏フェスとの相性も抜群ですね。
ドラマで言うと『ウォーターボーイズ』的なテンションですかね。
【② “シティポップ的世界観”に見る夏】

次に、シティポップ的世界観と名づけましたが、いわゆる「夜の都会」や「海」などのアダルトなイメージとしての夏です。
シティポップとはそもそも、7、80年代に流行した、都会的で洗練されたサウンドを特徴とするニューミュージックの総称を指します。
「アダルト」という単語が、こちらの側面を形容するのに適したワードだと思います。
景色として楽しむ、孤独ながらも持ち合わせる強さに心を奪われる「海」のイメージ。
そしてディスコやナイトクラブに象徴される、東京の夜の危なくてエロチックなムードの漂う「都会」のイメージ。
また、それらに花を添えるように孤独や失恋の情景描写として街を彩る「雨」のイメージや、タバコやバイク、ワンナイトなどの危険でワイルドなアイテムなど、どれも「アダルト」なシティポップ的世界観なのです。
シティポップに関する記事はこれまでも幾度となく書いてきました。ぜひ、この際同時にご覧いただきますと光栄な限りでございますm(__)m
【③ “エモ”の象徴としての夏】

ここからが本題と言ってもいいですね。最後に紹介する夏は、近年日常語として定着した”エモ”についてです。
とはいえ、かなり漠然としすぎた表現でした。
主に、
◎ 儚さ
◎ 若さ
◎ 青春
◎ ノスタルジー
など、日本映画的なテーマで浮き出る概念を、総合して”エモ”としました。
— 日本映画に見る「夏」 —
この「日本映画」という表現が、こちらの夏を説明するのに非常に適していると思います。
しばしば日本映画では、学生の一夏の出来事が、青春や若さの持つ「儚さ」や葛藤などに焦点を当てて描かれてきました。
これは、「若さ」と夏の「儚さ」の相性が非常に良いからです。
日本人は、「終わり」に美しさを感じる生き物です。花が咲き誇るよりも、花が散ることを1000年前から歌として詠んできました。
線香花火が、なぜ日本の映画や本で多く描かれているか分かりますか?火が落ちる時、夏が「終わった」気がするからです。作中で描かれる、出会いや恋の終焉の象徴として登場させるのです。線香花火に限らず、打ち上げ花火にしても同様です。
武士の時代、「切腹」は勇士の象徴でした。味方のために、殿のために、あるいは国のために死ぬことは、カッコよくてエラい行為だったんです。「終わり」に対する美意識は、そんなところから日本人の心に潜在的にあるのです。
こうした由来から、「儚さ」は特に日本で、芸術のテーマとされがちでした。青春や若さも、同時に儚さの象徴としてしばしば描かれてきました。こういった概念(まとめて”エモ”)の象徴として、自身の持つ性質ゆえに相性の良い「夏」は、幾度となく映画や本の舞台に選ばれてきました。
◎ 2021年公開の『明け方の若者たち』でも、恋の終わりの象徴として線香花火が描かれました。

◎ また、2022年公開の『ちょっと思い出しただけ』では、7月26日の一日だけを6年に渡って描いていました。やはり夏なんですね。

◎ 2025年公開の『ルノワール』では、とある女の子が一夏のトラウマになりうるさまざまな出来事を、純粋さゆえに冒険的に接近していくさまが描かれていました。舞台は主に夏でした。

◎ 「君の名は。」 (2016年)

そして、今回特筆してお話ししたい日本映画が、『君の名は。』です。『君の名は。』は、まさに夏を舞台にした、このような概念の象徴的な映画でした(むしろ、『君の名は。』以降、このようなテーマの夏映画が急増した気がしますが)。
現代の若者には、『君の名は。』が、”エモ”の夏のイメージの形成に大いに貢献している気がするのです。『君の名は。』が青春時代に教えてくれた夏が、現代人にとっての夏なんですよね(ちなみに新海誠監督の次作『天気の子』では、先述した「花火」が登場しますね)。
花火が「終わり」の象徴であるように、夏特有のものは全て、何か概念的なシンボルとして描かれています。
例えば、祭りや墓参りなどは、「ハレとケ」、「彼岸と此岸」と言ったような霊的なイメージの象徴とされがちです。
これらの概念は、日本映画ではわかりやすく登場しますが、音楽ではどうでしょう。日本映画に対する、さまざまな邦楽から見ていきます。
— 音楽に見る「夏」 —
夏の中でも、お盆やお彼岸などの霊的な部分や死との関連は、ある種の「儚さ」とも相まって、芸術のテーマとしてしばしば用いられてきました。音楽でも同様です。
中でも、特にそのような概念を可聴化したようなバンドが、スピッツです。
◎ スピッツ

君の青い車で海へ行こう
おいてきた何かを見に行こう
もう何も恐れないよ
そして輪廻の果てへ飛び下りよう
終わりなき夢に落ちて行こう
今変わっていくよ
「青い車」 / スピッツ
スピッツは、常にエロや死を裏テーマとして描いている気がします。「ロビンソン」や「水色の街」、「未来コオロギ」など多くの楽曲で登場する「川(河)」とは、おそらく彼岸(あの世)と此岸(この世)を繋ぐ三途の川でしょう。
スピッツには、夏の曲が多いです。
「プール」や「渚」、「チェリー」や「青い車」、また「海を見に行こう」や「夏が終わる」など。
加えて、夏を表す決定的なワードがないにしても、夏に聴きたい楽曲も多く存在していますね。「流れ星」や「スターゲイザー」など。
スピッツには同時に、夏ではなくとも「儚さ」や「若さ」、「青春」をテーマにした楽曲も非常に多く存在します。
「冷たい頬」や「夜に駆ける」、「ガーベラ」や「ロビンソン」など。
スピッツの話をしすぎました。が、スピッツに限らず、夏の概念的なテーマを追求した楽曲はどれも名曲として邦楽史に残っています。
◎ 2000年代のエモ文化
夏を舞台に、花火をモチーフに、「若さ」というテーマを追究し続けたバンドが残した、歴史的な名曲が存在します。それが、フジファブリックの「若者のすべて」です。
2000年代に象徴的な”エモ”文化は、さまざまな夏の(青春や若さをテーマにした)名曲を生み出しました。
◎ 「若者のすべて」 / フジファブリック
◎ 「天体観測」 / BUMP OF CHICKEN
◎ 「エイリアンズ」 / KIRINJI
◎ 「ばらの花」 / くるり
これらの楽曲は、全て若さや青春をテーマにしたものです。ほとんど夏の季語は存在しませんが、どれも舞台は夏を思い浮かべてしまいます。
2010年代以降も、このような楽曲はしばしばリリースされ続けてきました。本当に、日本人はこういったテーマが大好きなんですね。
◎ 「クロノスタシス」 / きのこ帝国
◎ 「花に亡霊」 / ヨルシカ
◎ 「灰色と青」 / 米津玄師
◎ 「なんでもないや」 / RADWIMPS
2000年以前は、どうだったんでしょうか。
70年代のフォークシーンは、日本人の夏に対する概念の、最初の音楽的な言語化だったのではないでしょうか。
例えば、はっぴいえんどの「夏なんです」。
加えて、吉田拓郎は多くの夏を言語化してきました。概念的な意味は深いところまではまだ及んでいませんが、目に浮かぶのは変わらない景色です。
名盤『元気です。』収録の、「夏休み」や「旅の宿」などが印象的。
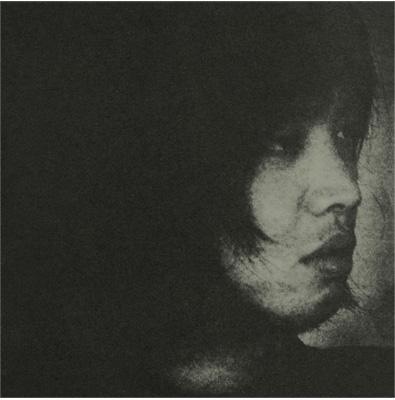
◎ 痛みや快楽、自堕落への美意識
わざわざ特筆して説明はしませんでしたが、儚さや若さという言葉の中には、エロチックな概念も当然及んでいます。特に、過ちやトラウマといった意味でのエロが多い印象です。痛みや自傷行為、自殺などを美化する、広い意味でもあります。
火の燃焼と同時に消えてゆくタバコは、花火と同じ意味でも多くの芸術作品に登場しますが、同時に命をむしばむものとしての(自傷行為や緩やかな自殺行為)モチーフでもあります。
また、自傷行為は自身の存在証明でもあり、痛みは生きている実感を与えてくれるのです。
◎ 参考: 『蛇にピアス』 (2008年)
— そして、日本を超えて世界へ —
このような概念は、日本人特有のものとしての認識が、私にはありました。しかし、近年登場した、世界的ファッションリーダーがその固定概念を打ち破りました。
◎ NewJeans

NewJeansは、今でこそ世界的アイドル/アーティストというイメージでしょうが、彼女たちの鮮烈な登場の理由を覚えていますでしょうか?
NewJeansは、ファーストEPを経て、「Ditto」の大ヒットで日本へ渡日しました。
「Ditto」の楽曲やミュージックビデオは、「若さ」や「青春」、「儚さ」や「ノスタルジー」といった概念そのものでした。その姿とその音に、世界中の全世代の老若男女が懐かしさと儚さへの共感で湧き上がったのです。こんなヒットの仕方は、世界初でしょう。というか、カルチャーやコンセプトが一周した結果とも言えるでしょうね。NewJeansは、衝撃的で唯一無二な存在でした。
詳しくは、以下の記事をご覧くださいm(__)m
NewJeansは、本当に儚いものとなりました。が、それでも夏の象徴として皆の心に生き続ける存在となりました。
日本映画や音楽などのカルチャーが示す、夏の固有な概念が、少しでも海を渡ってくれたことが、私はこの上なく嬉しいです。

以上、日本の夏についての考察でした。これからも研究を続け、より良い言語化が皆さんの前で出来れば何よりですね。
本日もご愛読ありがとうございました!それではまた(╹◡╹)

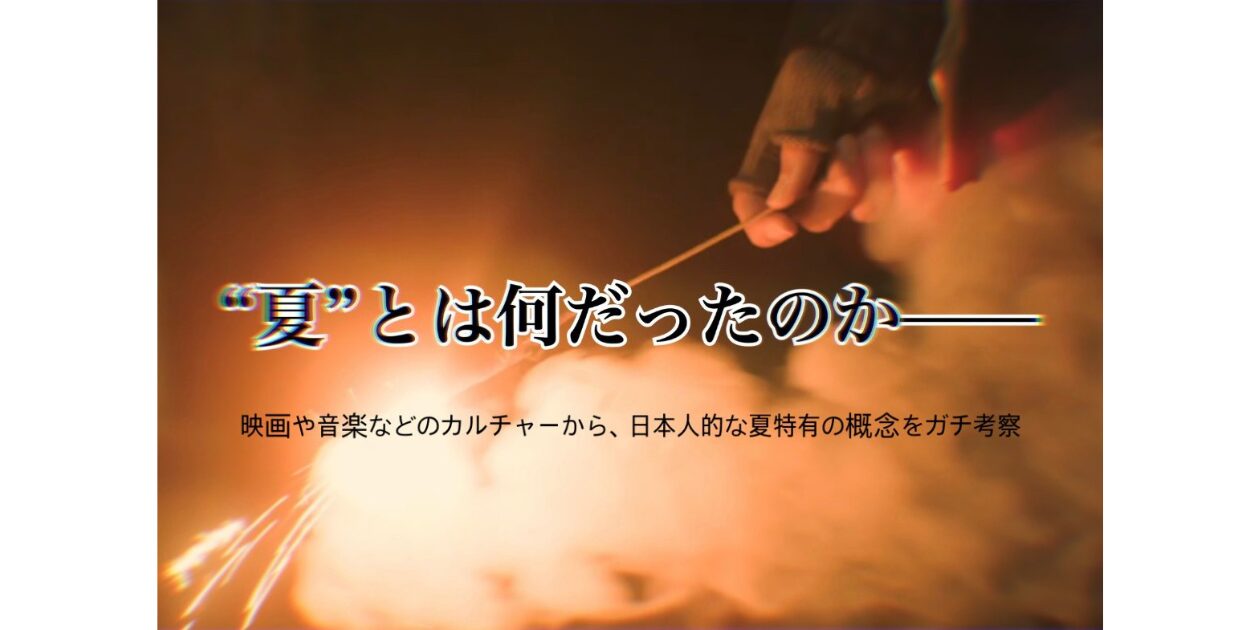

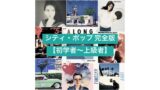





コメント