HIROSEのミュージックバーへようこそ。こちらのブログでは、音楽を中心としたさまざまな情報を気まぐれに発信しています。
今回は、米津玄師について音楽的視点から論じてみたいと思います。こないだ、ワタクシ五度目の米津玄師のライブに参加してきまして、ひどく感動いたしました(定期)。そこで、せっかくなら特集を組んでみようと、そういうワケでございます。米津玄師を毎日追っている中で、実は彼、世のポップシーンの変化に凄く適応しながら生きているんじゃないかと気づくようになりました。ということで、Lemonのリリース以降の彼の音楽的冒険を、音楽的見解から紐解いていきたいと思います。言うても、私は批評家でも学者でもないので非常に浅いですが(素人眼で)。それではどうぞ
【「Flamingo」の革命】
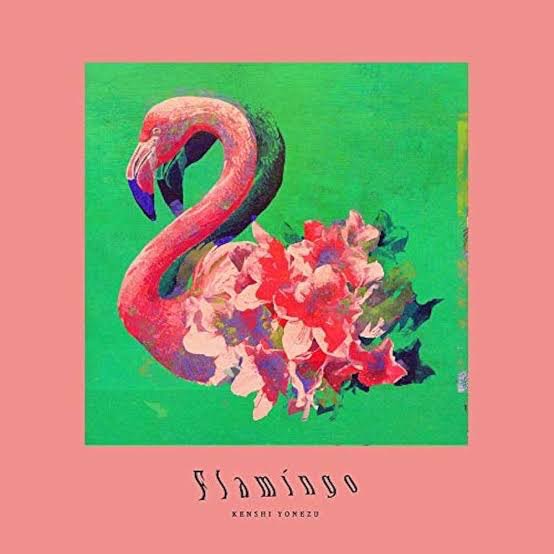
Lemon以降初のシングルとして、待望のリリースがありました。それが「Flamingo」。当時のリアルタイムで待ち遠しくしていた私は、この楽曲を初めて聴いた時、度肝を抜かれました。
米津玄師は、近年のR&Bに強く関心があるように感じます。そんな中で、メロディアスなベースのリフを中心とした、非常にブラックミュージック的なアプローチをしたのには、少し驚きがありました。加えて、イントロの調を外したクセのあるボーカルチョップや、歌詞や歌い方が象徴する”和”のテイストなど、一つのジャンルや系統に囚われない「米津玄師」というクロスオーバージャンルの開拓が、この時をもって始まったような気がします。色々な意味で、Flamingoのリリースは米津玄師の大衆に対する挑戦の心を感じましたね。
【「パプリカ」のセルフカバー】

「パプリカ」のセルフカバーは、米津玄師の音楽史上においてかなりエポックメイキングな瞬間であったと、今となっては思います。米津玄師の編曲家(アレンジャー)としての実力は、過去にも幾度として感じれる瞬間がありました。しかし、本当の意味で、彼の実力が”マジ”であったことが、本楽曲をもって分かったような気がしました。というのも、同じ楽曲(約一年前にFoorinに「パプリカ」を提供)ながら、編曲力によって真逆のイメージを持たせたのです。Foorinのパプリカには、明るくあどけないイメージがあります。むしろ、たまに顔をのぞかせる瞬間以外に、マイナスな感情は楽曲から感じられません。しかし、対する米津玄師のパプリカには、哀愁や寂しさが強く漂います。例えるならば、Foorinのパプリカは7月の夏、米津玄師のパプリカは8月の夏といった印象です。それも、夏休みと晩夏のような、対照的なイメージを持っています。この編曲力の高さは、今後のプロデューサー的側面において、強くその実力を活かすことができると思っています。
【「Pale Blue」以降の音楽的確変】

むしろ、ここからが本題といったところです。「Pale Blue」期の彼は、日本のみならず世界のポップシーンの流れに適応しようとしていました。米津玄師の11枚目のシングル、『Pale Blue』の収録曲は、「Pale Blue」「ゆめうつつ」「死神」の3曲でした。そして、その全てにおいて彼は、自身の基本の楽曲構成である、「1番2番Cメロラスサビ」という形を、変えることにしたのです。
当時のJ-POPシーンは、YOASOBIや髭男の圧倒的な活躍が目立ちました。そんな中、よりミニマムに、そして複雑になされる楽曲展開がJ-POPのヒットナンバーの「基本形態」となり、Cメロを2番の「後」ではなく「中」に置かれることが多く見受けられるようになりました。そして、元来のいわゆるCメロ(ラスサビ前のもの)orラスサビが、楽曲において省略されることが非常に多くなりました。
そして、「Pale Blue」「ゆめうつつ」「死神」の3曲を見てください。前2曲は、Cメロをラスサビとして扱い、飽きさせない楽曲展開を構築しています。また、「死神」に関しても、Cメロを2サビ前に配置することで、同様の効果を期待していますね。以前の米津玄師の楽曲では、あまり多くは見られなかった楽曲の構成ですが、しっかりと時代の変化に対応しているのがさすがだと思いました。
【「KICK BACK」と転調】

2022年、世は「転調」ブームでした。髭男の「Cry Baby」を皮切りに、髭男の「ミックスナッツ」やKing Gnuの「逆夢」、藤井風の「燃えよ」やYOASOBI各曲のラスサビ半音転調など、蔓延るヒットナンバーのほとんどが「転調しまくる」という異常なムーブメントが発生していました。しかし、この男は間違いなくこんなムーブメントにも乗っかっていきます。「KICK BACK」のリリースは、単にヒットしたというだけではなく、米津玄師の転調ムーブメントへの挑戦であったと思っています。高速テンポに、目まぐるしく変わりゆくメロ展開が、ころころと転調しながら繰り出されてゆくという、まさに当時のポップシーンを象徴するような楽曲でした。この適応力凄いですよね。やろうと思えばなんでもできちゃうという、、
【「LADY」とイージーリスニング】
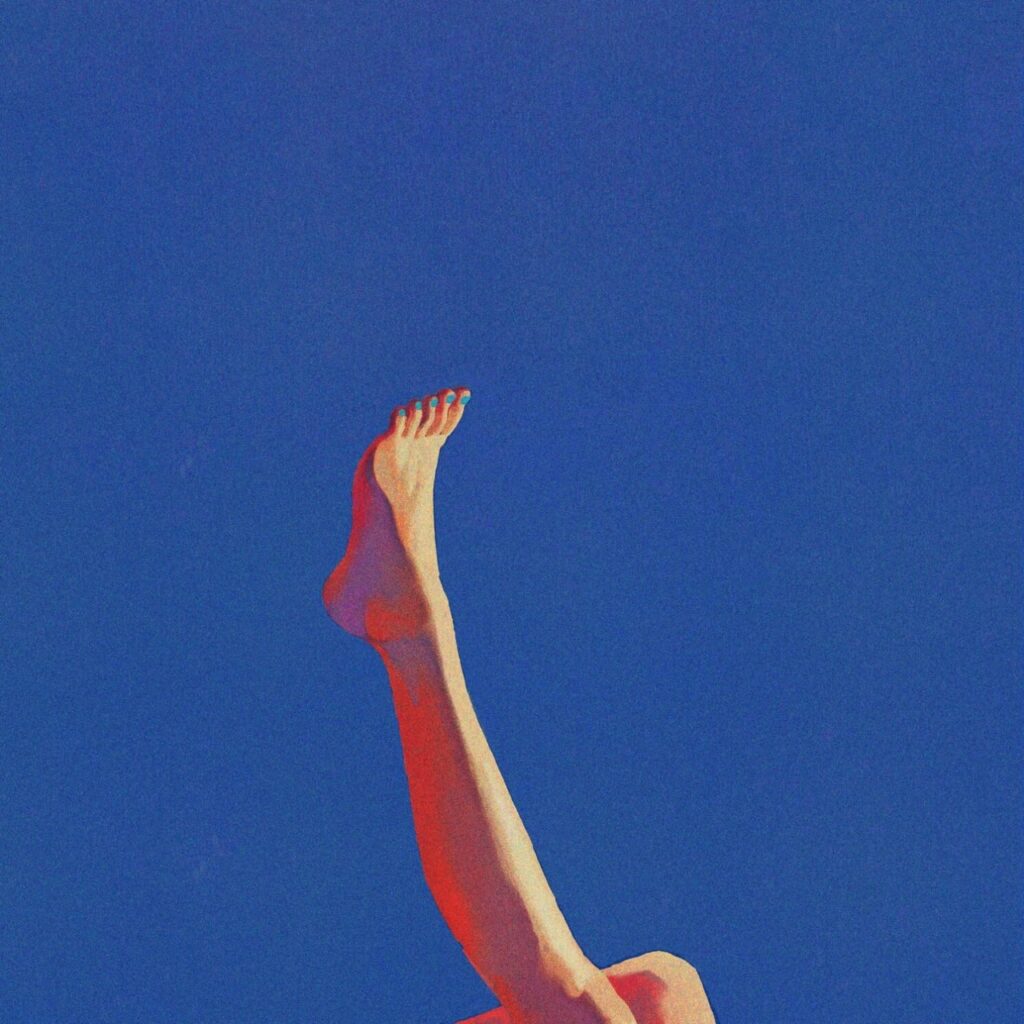
「LADY」は、近年の米津玄師の楽曲の中でも、むしろ異彩を放っているとも取れるほど、シンプルで聴きやすいです。当ブログでは、近年のポップシーンを語る上で「NewJeansの出現」を大きなターニングポイントと示すことが多いですが、今回もやはり彼女らの影響が、ポップシーンに、そして米津玄師に波及しているような気がしました。
NewJeansが提示した新たなポップスの在り方として、「あえてのシンプルさ」というのがありました。要は、複雑化や情報過多していった近年のポップシーンに、あえてシンプルで日常的な楽曲を流行らせたわけです。詳しくは、以下のNewJeans入門の記事にて扱っていますので、未読の方はこちらもぜひ。
米津玄師はそんな、いわゆる「イージーリスニング」の要素をJ-POPシーンにもたらしました。むしろ、近年のJ-POPの主流の形となってきていた「短い曲」の構成から、複雑性の要素を抜いたと言うべきでしょう(コード進行もCメロ以外簡素)。同じく短い構成の楽曲と言えども、当時のJ-POPには転調ブームや複雑なコード進行のものが溢れていて、J-POPのトップアーティストが洋楽的なシンプルな楽曲をシングルリリースすることは、逆に久しいような感覚がありました。その影に(直接的な影響の有無はわかりませんが)NewJeansの登場が影響していたと、私は考えています。
【「BOW AND ARROW」とNewJeans】

「LADY」以降、「月を見ていた」(FF)や「地球儀」(『君たちはどう生きるか』)、「さよーならまたいつか!」(朝ドラ)など、立て続けにドデカい(にしてもデカすぎる)タイアップがあり、あまり音楽的冒険がしにくい環境があったように思います(その直後ニューアルバムがリリースされることになりますが、今回は割愛)。
そんななか、「LADY」以降、「毎日」や「Azalea」など、イージーリスニング的な楽曲が米津玄師の新たな主流の音楽の形になっていきましたが、その影にNewJeansの影響があったのではないかという推測を先ほど立てさせていただきました。それに加えて、NewJeansの楽曲が80~90年代のブラックミュージックを参照していることから、ドラムンベース等のブレイクビーツがポップシーンにて再流行したことに、ここでは触れていきたいと思います。つまり、「BOW AND ARROW」は、一昔前のブラックミュージックの要素を引用したNewJeansからの影響を、どうしても感じざるを得ないわけです。それも、世界的にブレイクビーツ(ドラムンベースを含む)の要素をイージーリスニングに加えるムーブメントが僅かながらあったと記憶しているので、そういう意味で、米津玄師はまたも時代に適応してしまったのです。あえてパンチのある目次を狙って「NewJeans」と大きく書いてしまいましたが、近年のポップシーンにおけるNewJeansの影響力の大きさと、米津玄師の流行に対する適応力や挑戦の心がわかると思います。にしても、コレ名曲すぎる。近年の米津玄師楽曲の中で一番好きなんですね、私。

以上、米津玄師の音楽的変化についてでした。こう見てみると、かなり時代に順応しながら生きていることがわかりますね。凄い。
本日もご愛読ありがとうございました!それではまた(╹◡╹)



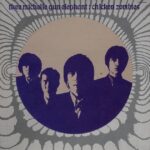
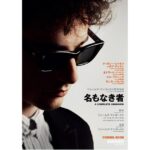
コメント